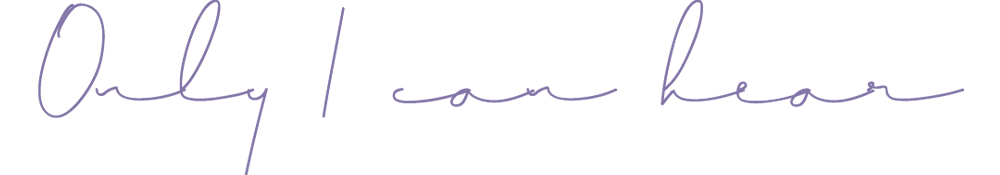
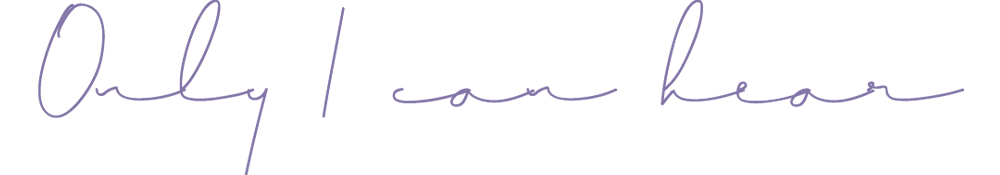

声と声の間で感情が動き意味が兆す、その現場を見せてくれる
谷川俊太郎(詩人)
聴こえない親と無理に同じになろうとしなくていい。聴者の世界にどうにか馴染もうとしなくてもいい。
狭間の世界に生きるコーダであることを、そのまま受け止める。周囲との“違い”を否定せず、塗り替えようともせず、ただそのまま、受け止める。
ただ、それだけでよかったのだ。
五十嵐大(ライター、エッセイスト)
「目で見る」コーダやろう者たちを追う中で、松井至監督もまた、そうした画面の切り取り方や映像で語らせるやり方を身につけていったのだろう。葛藤は苦しいけれど、その葛藤から豊かなものが産み出される希望もあると感じさせてくれる、そんな作品である。
澁谷 智子
(成蹊大学文学部 現代社会学科 教授)
ろう者と聴者の間に存在するCODAたち、できればろう者になりたいという気持ちがあるのははっとするものでした。本当の多様性を確保するためにとても参考になる作品です。
ピーター・バラカン
居場所のなさや自身のアイデンティティについて悩み、語るコーダ。自ら選べない厳しい現実にあるコーダたちだが、それぞれの生き方の選択はどれも尊く、観る者に思いがけず前向きな気持ちをもたらしてくれる。目の前に存在する人を先入観なしにまっすぐ見ることの大切さが伝わってくる作品だ。
青野賢一(ライター、選曲家)
「ろう者でもなく、聴者でもなく、私はコーダ」という語りが胸に響いた。コーダは、ろう文化と聴文化の間で、ポジティブにいえば媒介者、ネガティブにいえば引き裂かれているとよく言われる。しかし自分はそんなスキマにいるのではない! と。その力強い宣言が、両親への情愛とセットで伝わってくる。別々のコミュニティの住人がたまたま家族という岬で出会った――そんな感慨がやってきて、鼻の奥がツンとしてきた。
白石正明
(医学書院
「シリーズケアをひらく」編集)
手を使って話し、愛し、悲しむ――ろう者を親に持ったアメリカのコーダたちの人生と悩みを見せる作品。コーダのアイデンティティが固有であることだけでなく、各々の環境によって異なることをも示唆する。なにより、親兄弟のように「ろうに生まれたらよかった」と告白するOHCODA(Only Hearing CODA)の話を通じて、“ろう”が障害でなく他の世界へと向かう入口であることを悟らせる。ろう者でもなく聴者でもない、時にはろう者でもあり聴者でもある。それがコーダという存在であることを、私はもう一度確認する。
イギル・ボラ(コーダ、映画監督、作家)
松井監督のパッションにより大きく、色んな人を巻き込んでコーダが2つの世界の狭間で揺れ動く様子を鮮明に描いたドキュメンタリー映画になっていると思います。この映画は「孤独」を克明に見せており、もっと多くの方に見てもらいたい映画です。私自身も松井監督の情熱に突き動かされました。この映画に関わることができて光栄に思います。ありがとうございました。
那須英彰
(ろう俳優、手話ニュースキャスター)
コーダのことも、ろうのことも、聴者のことも、映画を通じて知れること感じることいろいろありました。コーダじゃなくても、みんな自分の居場所が必要だし、心の奥底まで他人のことを知れることはなかなかできないかも知れない。ナイラの最後の言葉に尽きると思いました。
ゑでぃ鼓雨磨(ゑでぃまぁこん)
サイレント時代の怪奇映画で活躍した名優ロン・チェイニーの伝記映画『千の顔を持つ男』を最近観て、この俳優が聾唖者の両親に育てられたことを初めて知った。この映画で、聾者に対して聴者が露わにする嫌悪感や恐怖心、コーダであるチェイニーにしか分かりえない苦痛もドラマティックに描かれていて、観ていて苦しくなったものだった。この映画から60年も経って少しは世の中もマシになっているかと思いきや、そうでもないらしい。ただ、この映画ではそうした「世の中」との乖離や軋轢に苦悩し続けるばかりではなく、各人の冷静な主体性から描き出される「コーダ学」的な思索が中心に見えてくるのが特徴的で、そのどこか甘美で超然とした世界に門外漢の我々を引き入れんとする強い姿勢には、十分な説得力がある。
澁谷浩次(yumbo)
私もきっとコーダの彼女たちのことがわからないさびしさを知りました。それぞれのことばで分けあい切れないものがあり、だけど漂ってどこかにあると思うとなにか希望も感じます。
南阿沙美(写真家)
コーダであることは「居場所を奪われた者」として生きることだ。
「毎日何となく孤独」「ろうになりたかった」「放っておいてくれ」
この映画では、浮遊感のある映像と音楽でコーダの孤独感、コーダ同士の交流が描かれる。
その姿が沁みてくる。なぜか。私達の誰もが「故郷喪失者」だからだろう。
加藤学(博渉家)
言葉はどのように開かれるか。
体をねじって息と一緒に湿気のように湧き上がってくる。意味は雨粒のように皮膚の上ではじけ、すずしい風のようにどこへでも行ってしまう。
何かわかることはないかと思う。わかるということは治癒だと知っているからだ。例えそれが形のないものであっても、わたしたちはいつでも半分だけ留守の体を用意して、言葉がそこにやって来るのを待っている。
小内光(詩人)
『私だけ聴こえる』は、私があまり知らなかった世界へ深く導き、幸せな気持ちにしてくれた。コミュニケーション、家族、成長、自分らしさを見つけることについて親密に語っており、この素晴らしい子どもたちが人生の中で自分の道や居場所を見つけることにとても感動し、心が揺さぶられた。そして、テニスコーツ独自のサウンドトラックが、それを見事に音楽に置き換えてくれている。
Markus Acher (The Notwist)
「私はろうになりたい」というナイラの言葉は、映画が終わる最後の瞬間まで柔らかくて曖昧な輪郭のままだった。そこに光を感じました。
加藤かなた(Ka na ta)
この映画を観てコーダという存在を初めて知りました。
ろう者とコーダが手だけではなく、表情や体も使って表現しているのを見て、伝えるというのは、本来このように全身使ってやるものなのだとハッとしました。聴者は、声と耳に頼って話すことがほとんどで、目を見ないで話すこともよくあります。しかし目や表情というのは心情を大きく映すものです。そのことを十分理解しているのが手話言語者なのではないでしょうか。
豊穣な表現方法を持つ「ろうの文化」で育ちながら、聴者でもあるコーダが、ろうの文化を知らないのに勝手に決めつける聴者の態度に戸惑うのは当然で、思春期ならなおさらでしょう。コーダ同士であれば発話とあわせて手話が「字幕みたいに」機能し本来の自分でいられるのに、聴者のみの場所では両極の世界に引き裂かれてしまう…。「二重の世界」「居場所が欲しい」「同情しないで」というコーダの切実な声によって、何かを失くしてしまっているのは聴者のほうだと気付かされます。
登場するコーダの心情が音になったようなテニスコーツの音楽が人々を紡ぎながら、映画は両親と庭で雪合戦をしたナイラがゴロンと雪の上に寝そべって終わります。雪の中からは彼女の心の変化を表すかのようにたくさんの新芽が顔を出し、応援しているようにも見えました。私もその新芽の一つになりたいです。
工藤夏海(美術家)
インタビューに答えるコーダの言葉には、白か黒かと単純に割り切れない不条理を知り尽くしているがゆえの戸惑いが含まれている。本作でぼくが感じいったものは、言葉ではなく、シーンごとにめまぐるしく移り変わる表情だった。
ろう文化と聴文化。ふたつの世界を行き来しながら深まる悲しみを抱えつつ、いっそう華やぐ表情が、あまりにも人間で、何度も胸に迫った。
齋藤陽道(写真家)
家族と外の世界とのはざまで多感なときを過ごす、どこか大人びたコーダの子どもたち。言葉やまなざし、揺れる心に映し出されるのは、ここに生まれてきたことへの葛藤と自覚の萌芽。他を知り、自分も他のひとつだと感じることで、窮屈だった世界や心根が少しずつ広がる。人との違いに違和感を覚えている方に観て欲しい。身近な人たちと語らいたい。他と他がともに生きる世界を、もっとみんながあたりまえに思えるように。
甲斐みのり(文筆家)
真摯にコーダに添い制作されたことが伝わる。映画のあらゆるシーンに、私たちコーダが慣れ親しんできた情景が描かれ、ときにさまざまな感情が去来し気持ちが揺さぶられる。登場するコーダに心を重ね苦しくなる場面は、映像の美しさに救われる。この映画をとおして、どこかで独りで頑張っているコーダに届いてほしい、「ひとりじゃないよ」と「私は私でいい」。
中津真美
(東京大学バリアフリー支援室、
J-CODA)
自分には4歳の娘と、1歳の息子がいます。 娘が1歳半の時には車椅子をおもちゃにして乗りこなしていました。 2歳のときに「パパはなんで車椅子なの?」と聞かれました。 息子を抱っこして娘と一緒に公園に行くと、興味を持ってジロジロ見てくる子がいます。 そんなとき、娘は「こわい」と私の後ろに隠れます。 「障害がある家族がいても、かわいそうではなくて、幸せな人生が送れる」 そんな当たり前のことを確認する映画になったら嬉しいです。
かんばらけんた
(車椅子ダンサー/
Wheelchair Dancer “Kenta Kambara”)